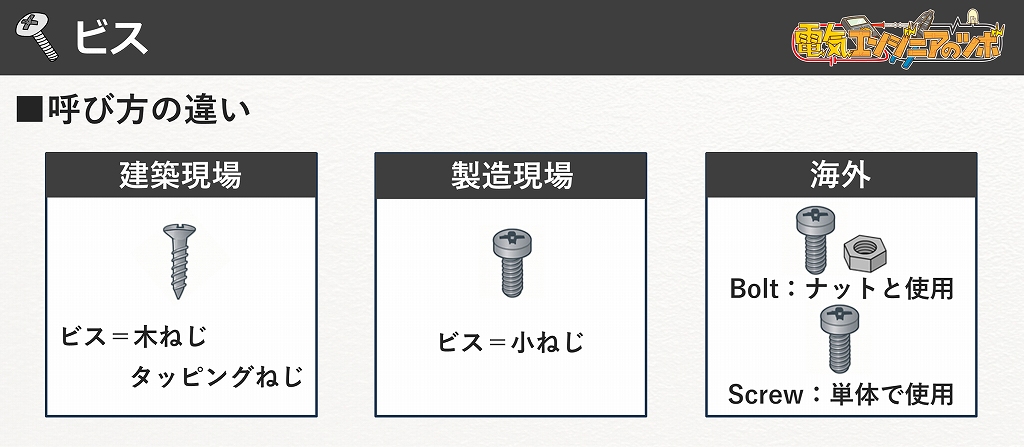いきなりですが、下画像のネジが入った袋を見てください。
ラベルには「ボルト」「ねじ」「小ねじ」「ビス」など、いろいろな名前が書かれています。
では、これら全部の違いを説明できますでしょうか?
実は、どれも広い意味では“ねじ”の仲間ですが、JIS規格では、それぞれにしっかりとした定義があります。
今回の記事では、「ねじ」「ボルト」「ビス」の違いを紹介していきます。

動画版もあります!
ねじ(ネジ)とは

図の左側のように外側にねじ山があるものを“おねじ”、図の右側のナットのように内側にねじ山があるものを“めねじ”と呼びます。
つまり、ボルトもビスも、すべて“ねじ”という大きなカテゴリの中に含まれます。
ボルトとは

頭部は六角形が代表的ですが、他にも四角形やフランジ付きなどさまざまな形があります。
スパナやレンチで回して締めるのが一般的で、大きな力でしっかりと締結できます。
ボルトはフレームや構造部材で使われることが多く、タップ穴加工よりもナットや溶接ナットとの併用が一般的です。
タップ穴
タップ穴とは、ドリルで開けた穴の内側にねじ山を切った穴のことです。
小ねじとは

呼び径の目安は M1.6~M10 ほどで、M12以上は一般的にボルト扱いとなります。
長さは分類には関係しません。

小ねじはカバーや電子機器の取り付け、板金部品の固定などに使われます。
固定するときは、ナットを使わずにタップ穴に直接ねじ込むケースが多いです。
ビスとは
“ビス”はJISでの正式用語ではなく、現場や分野によって意味が変わります。
この呼び方の違いが混乱のもとになっています。
例えば、建築現場では「ビス=直接材料に打ち込むねじ」という認識が強く、木ねじやタッピングねじ、あるいは小ねじをビスと呼ぶ場合があります。
設備の製作現場や製造現場では「ナットを使わない小さなねじ」をビスと呼ぶ場合があります。
たとえばスイッチボックスのカバーを固定するときに「M4ビス持ってきて」と言われましたら、M4小ねじのことを指す場合がほとんどです。
参考:海外での呼び名について
参考までに海外では“Bolt(ボルト)”はナットと使うねじ、“Screw(スクリュー)”は単体で使うねじ、という整理が一般的だそうです。
まとめ
ポイント
・ねじは総称
・ボルトはナット、またはタップ穴と組み合わせて使用
・小ねじは呼び径M1.6~M10のねじ(JIS B 1111など)
・ビスは正式な規格用語ではなく、現場用語で意味が変わる
この違いを知っておきますと、現場での会話や図面の読み取りがスムーズになるかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
参考文献
・JIS B0101「ねじ用語」
・JIS B1111 「十字穴付き小ねじ」
JISC 日本産業標準調査会より
※アカウント登録必要